
みなさん植生活楽しんでいらっしゃいますでしょうか?
今年も暑いですね〜、私達だけでなく植物もバテたり・ストレスを感じています。
今回はハイポネックスより出ている植物用活力剤「リキダス‐RIKIDUS‐」の正しい使い方をご紹介いたします。
よく発根比べみたいな企画で使われていますが、本来は根のある植物の毛細根にアプローチをしていく活力液だと思っています。
根の仕組みも一緒に解説しながらリキダスの正しい使い方をマスターしてより園芸を楽しみましょう!
そもそも活力剤ってなんだ?
よく例え話で肥料は植物にとっての食事、活力剤はサプリメントなんて言われたりしますよね。
活力剤とは、読んで字のごとく植物に活力を与える成分を含む資材です。
肥料とは別物とお考えください。
肥料とは「窒素‐N、リン酸‐P、カリ‐K」がそれぞれ0.1%以上、あるいは2成分の合計が0.2%以上含むものが日本の法律で肥料とされています。(単肥はまた別ですが)
活力剤は、上記の「窒素‐N、リン酸‐P、カリ‐K」の三要素が肥料の規定に満たないものや微量要素やビタミン・アミノ酸など三要素以外で植物の生育を活性化する成分を配合したものなどの総称です。

少し酢っぽい匂いがします
これであぁなるほどってなる人も少ないかと思います。
少し植物の必須元素についても解説していきましょう!知るとより肥料・活力剤が面白くなりますよ。
植物の生育に必要な17種類の必須元素
必須元素とは植物の生育に必要不可欠な元素で、植物にとってたくさん必要なものとほんの少しでいいものとがあり、それぞれ多量元素と微量元素に大別されます。
必須多量元素(9種類)
まずは、炭素‐C、水素‐H、酸素‐O です。あれ N・P・Kじゃないの?となるかも知れませんがこちらは我々が何か追加で加えるものではなく植物自身が大気中の二酸化炭素(CO2)、または水(H2O)から供給されるため通常肥料として与える必要がないものです。
理科の授業でやった光合成や呼吸とかの話のアレですね。(私は記憶にありません)
続いて三大肥料の 窒素‐N、リン酸‐P、カリ‐K やっと知ってる単語が出ましたね。
それぞれ葉肥(N)、実肥又は花肥(P)、根肥(K)なんて呼ばれたりしますよね。
葉肥っていうんだから窒素は葉にしか働かないかというとそうでもなくて
| N | 光合成に必要な葉緑素や核酸等の構成元素で葉や茎の生長に関与する 窒素過多‐軟弱化(人でいうメタボ)、病害虫や冷害への抵抗性↓ 窒素不足‐葉の淡黄色(いわゆる肥料切れの葉の症状)、矮性 |
| P | 核酸・酵素の構成元素で開花・結実を促進する。実以外でも必要とされる。 活発な代謝を支えるATPや糖リン酸以外に細胞膜の成分にも使われる リン酸過剰症‐出にくいが結果としてMg・亜鉛・鉄欠乏を誘発し、開花・結実を遅延する |
| K | 細胞の膨圧維持による水分調整(浸透圧調整)に関与し、根の成長を促進する K過剰症‐出にくい。ただしカリウム過剰はカルシウム・マグネシウム欠乏を誘発 少ないと根は主根付近のみに形成、側方の根の成長は制限される |
なるなる!毎日あげてもいいけどこれを見ていると植物が吸えない時は垂れ流すか過剰に溜め込んで二次的な症状を誘発する可能性がありそうですね。
よって少なくとも室内で観葉植物を育てる際は、鉢がしっかり乾いている事と数日空けてから使う必要がありそうです。
上記の要素は、土壌に不足しがちなので、肥料として補給してあげる必要があると。
それだから液体肥料や固形肥料にはN・P・Kと書いてあるんですね。

正直 C・H・O(炭素・水・酸素)よりもこのN・P・Kの方がよっぽど有名ですね
ここからは少しざっくりでいきますよ
二次要素(カルシウム‐Ca、Mg‐マグネシウム、S‐硫黄)は、肥料の三大要素についで植物の要求が高い元素です。
| Ca | 細胞組織の強化、根の生育の促進する 過剰症‐出にくいが、拮抗作用によりMgやKの吸収を抑制 欠乏‐トマトなどでは尻腐れ、キャベツ・白菜では芯腐れが発生する ちなみに窒素不足、水分不足はカルシウム欠乏症を助長する |
| Mg | 葉緑素の構成元素(肥料に緑イキイキって書いてある理由ですね) 相乗効果でリン酸の吸収や運搬を助けます。 過剰症‐出にくい 欠乏‐Mgは葉と果実に多く含まれ、生育中〜後期に欠乏すると葉脈間クロロシス(※)が出現する ※葉の葉脈間に見られる黄化現象では、葉脈の緑色は残るので葉全体が網目状に見える |
| S | タンパク質、アミノ酸、ビタミンなどの生理場重要な化合物にかかせない元素 炭水化物代謝や葉緑素の生成を助ける働きもある 植物自体に過剰症状は現れないも、土壌の酸化や流れた先で老朽化水田などで硫化水素の発生原因へ |
リキダスでは、このカルシウムが全面に押し出されていますね。
カルシウム自体は、植物の欠乏しやすい部位としては先端の葉や上葉・新芽、花・果実などで移動しにくい成分といわれています。(根から葉先やらとたしかに移動距離も長そう)
これをしっかり目的の場所まで届きやすくするために配合されたのがリキダスなのです。
やっぱり根に刺激を与えて株自体の成長を促進させるものであると考えていいでしょう。
ここで出てくるのが特許取得もされているコリン、フルボ酸、アミノ酸の独自配合です。
それぞれ
アミノ酸→土の中の微生物を増やして植物にすぐ吸収されやすい形にする
フルボ酸→ミネラルやアミノ酸をコリンへ渡す
コリン→先端までミネラル・アミノ酸などを届ける
まるでポンプのように下から上まで運ぶことが出来るようになった資材なのです。
ちなみに最後に
植物の生育に不可欠だけどたくさんはいらない必須微量元素(8種類)
食事に例えると副菜でしょうか。植物としては構成成分ではなく、酵素的な作用が多くなりますね。
今回は名前だけ Fe‐鉄、Mn‐マンガン、B‐ホウ酸、Zn‐亜鉛、Mo‐モブリデン、Cu‐銅、Cl‐塩素、Ni‐ニッケルの8種類です。そのほかにも数種類有用元素なんてのもありますが今回は割愛させてください。
いや〜奥が深いですね。
簡単にまとめると
リキダスは根に作用してポンプの様にカルシウム始めとした、各種ミネラル(微量要素)が植物に活力を与える資材です。
リキダスの使用の方法
そんなの書いてあるじゃん!規定倍率に希釈して水やりみたいにかける
その通りでございます。さらにここからはワンランクアップして行きましょう。
上にも書いた通り根に作用することは分かりましたが、ここで問題なのはどこの根に作用するのか?
みなさまは根にも種類があるのご存知ですか?
少しだけ根の種類について解説していきましょう。

根の画像ですが、モジャモジャしているなかから太い根と少し細い根があるのは分かりますか?
根には大きく3種類あって
主根(一次根)、側根(二次根)、毛細根(三次根)と三つで出来ています。
水差ししたことある方は、イメージしやすいと思いますが
植物を水挿しているとニョキニョキと白い根が出てきますよね?→これが主根です。
主根の特徴としては、太くて比較的出やすいことです。
しっかりと根を土に伸ばして土台を作る子です。それぞれこんな感じの特徴があります。
〈根の出やすさ〉
毛細根<側根<主根 主根は出やすく、毛細根は出にくいと覚えてください
〈根のストレス耐性〉いわゆる根腐れや環境変化での枯れやすさです。
主根<側根<毛細根 毛細根さんは繊細です。生やしにくくてダメージを受けやすい。
〈根の役割〉
主根・・・窒素・水
側根・・・窒素・リン酸
毛細根・・・リン酸、カリ、微量要素 それぞれ役割が違う
上の必須微量元素の話もありましたが、微量要素は少なくていいけど必須です。
早い段階でこの毛細根を作ることが出来るようになるとより株が丈夫になりやすいといえます。
この話を土台に考えていきましょう!
リキダスは活力剤です。そして根の生育を促進するCa‐カルシウムを豊富に含んでいます。
カルシウムは発根にも作用しますが、特に微量要素を吸収する毛細根の発達を促す効果があります。
なるほどな〜ってなってくれました?(心配)
発根動画でよりリキダスは他の商品に負けていますが、戦う土俵が違うのです。
主根がある程度育ってからがリキダスの本領発揮出来る場面ではないかと思っております。
つまり発根させるよりも発根させた根に刺激を与え、毛細根を出させるために使えば良いのです。
ざっくりリキダスの効果まとめると
- ポンプのようにコリン・アミノ酸・フルボ酸の相乗効果で葉先までしっかりと活力を与える
- 根に刺激を与えるカルシウムが豊富に含まれており、毛細根の発達を促す
- 毛細根中心に根が発達することで肥料の要求量が増え、より栄養が吸収しやすくなる
自分で栄養を吸い上げられないとき、暑さ・寒さ・日照不足などストレスを受けているとき、根張りを良くしたいとき、根がある植物の植え付け・植え替え時の根の活力UPなどに使えますね。
さてやっと使い方です。ずばり肥料やバイオスティミュラント材を使用する前にリキダスを使うです。
例えば生育期、リキダス→液肥5000倍→水→リキダス→液肥5000→水というように
乾湿を繰り返しながらリキダスで根に刺激を入れてあげて、その後に肥料を与える事で根がしっかり動いて肥料等を吸収しやすくしてくれます。
リキダスだけでは、植物は育ちません。あくまでリキダスはサプリメントや副菜。
主菜はしっかりと肥料で補ってあげましょう!
私達は、植物の上の部分を愛でながら実際に育てているのは根の部分なのだと思います。
こうやってみるとインテリア性重視の透明鉢が流行るのも納得ですね。
根ってそれだけ魅力的ってことですもんね
有名な熱帯植物栽培家の杉山拓巳さんのオリジナル用土のベストソイルミックスも「よく分岐した根を作る」とおっしゃっていて上記で解説したようないわゆる側根や毛細根を充実させるためではないかなと考えています。(全然違ったらゴメンナサイ)
市販用土のおすすめ記事
リキダス使用時の注意点
混合液について
液肥と一緒に混ぜて使用する事も可能ですが、原液同士を混ぜるとカルシウムとリン酸が結合してリン酸カルシウムとなってしまい植物が吸収できなくなってしまいます。

ちょっとゲル状になります。

時間を置くと沈殿します
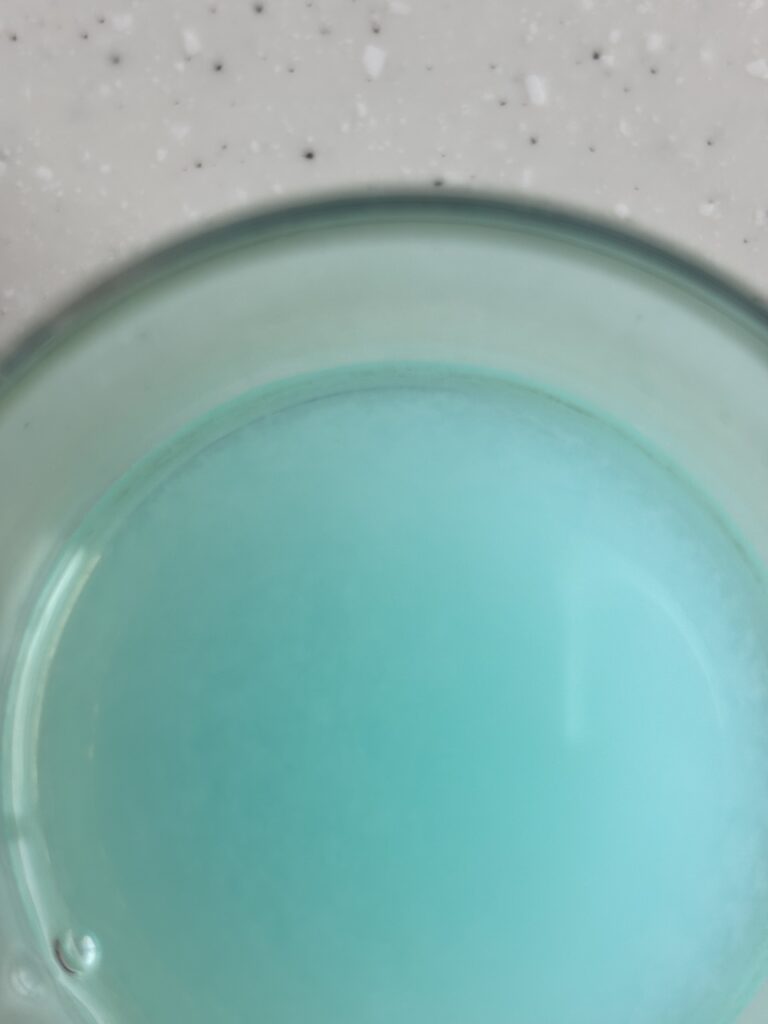
なんか浮遊物が、、、これがリン酸カルシウムかと思われます
◎解決方法としては、液肥を水と必要量希釈してからリキダスを追加するだけです。
通称 スーパー原液と呼ぶそうです。
葉の上の方までしっかりと栄養を届け、ワサワサの植物を作りたい時
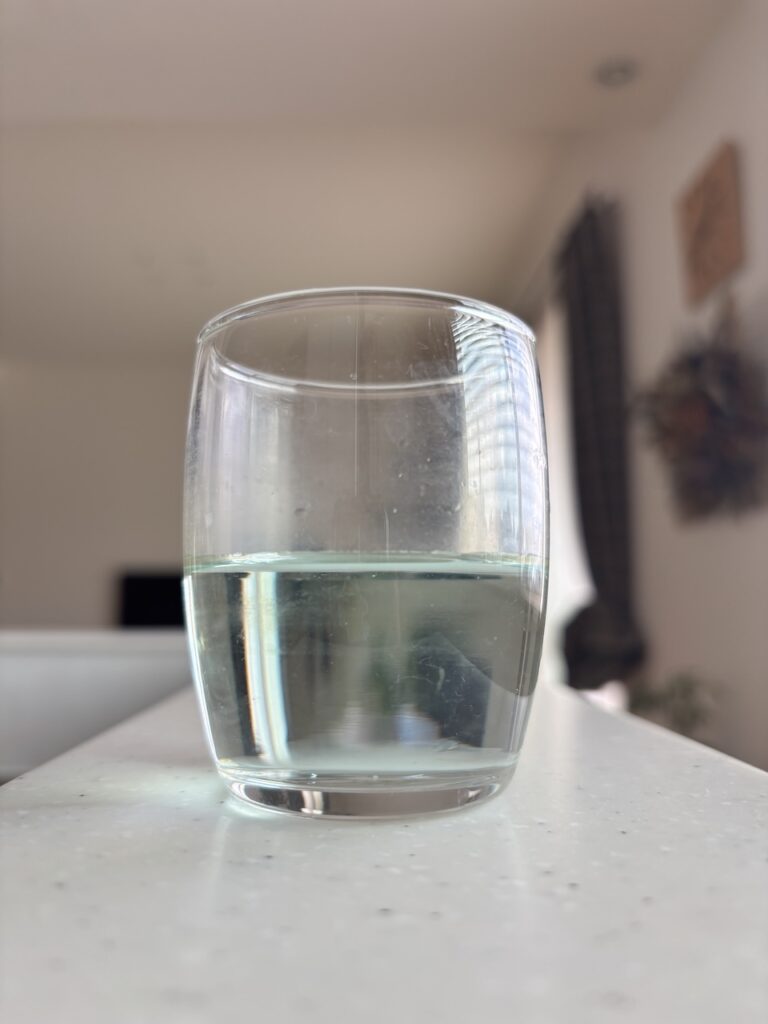
ただし時間が立つと温度などの条件によって徐々にリン酸カルシウムへ結合していきます。
混合液を作ったら作り置きせず、すぐに使い切りましょう!
その他の活用方法
微粉ハイポネックス→リキダス 通称 微粉スペシャル
方法‐微粉ハイポネックスを鉢の外側・乾いた用土の表面にすき込む→リキダスで水やり
根にしっかりと刺激+肥料を与える使い方
株をよりコンパクトにガッシリと育てる

一番左が微粉ハイポネックス
ココチップ✕リキダス
ココチップなどは一度乾燥してしまうと給水しづらくなります。
そこでリキダスで少し半乾燥状態にしておくことで植え付け後の活着と給水しやすい状態をつくります。
我が家では、ココチップ1L程度に10〜20ml程度のリキダスで希釈した水(リキダス水)で濡らして密閉容器で保存しています。
こうする事で微生物を増やすお手伝いもしながら、植え込み後の活着も早められます。
植え替えに使う株は、基本的には主根、側根は出ていますもんね。

ベラボン始めベラボン・プレミアム、ネコチップなどにどうぞ!
いかがだったでしょうか?
初心者にこそ使いたい資材、それが「リキダス」です。すごいぜ、リキダス(言いたいだけ)
皆様の植生活が日々楽しいものになるお手伝いが出来たら幸いです。
今日も良い一日を! ばーい!

今だけ100ml増量中だそうです!
もしすでにお持ちの方はバランスの良い食事として植物に違う活力剤で刺激与えてみませんか?









コメント